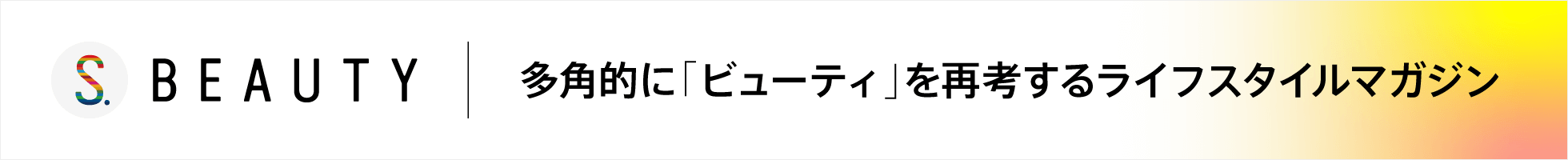リモート時代に浮かび上がる
近松門左衛門の「虚実皮膜論」
フィクションと現実が入り交じるこうしたエンターテインメントのつくり方を「虚実皮膜(きょじつひにく)」と呼ぶ。生み出したのは、江戸時代の人形浄瑠璃・歌舞伎作家、近松門左衛門だ。「虚構と現実が、薄皮一枚でないまぜになっているところに芸術の面白さがある」(皮膜=皮膚と肉のその間)という芸術論である。
近松は「虚にして虚にあらず、実にして実にあらず。この間になぐさみがある」と述べ、フィクションをすべてフィクションのみで構成するより、事実を絶妙な配分でミックスすることで、見るものを高揚させ、満足させることができると説いた。
例えば、近松門左衛門が書いた人形浄瑠璃・文楽の『曽根崎心中』は、江戸中期に大阪新地の女郎「はつ」と、醤油商平野屋の「徳兵衛」が、実際に曽根崎村で情死した事件が題材となっている。登場人物の名前や、最終的に曽根崎で心中した点をあえて史実そのまま用い、そこに浄瑠璃や歌舞伎特有の脚色が施されエンターテインメントに仕上がっている。
 浮世絵師・奥村政信が描いた、近松門左衛門の『曽根崎心中』の舞台〔PHOTO〕Getty Images
浮世絵師・奥村政信が描いた、近松門左衛門の『曽根崎心中』の舞台〔PHOTO〕Getty Images
鶴屋南北が書いた歌舞伎作品『東海道四谷怪談』も、江戸・元禄時代にあった「重婚事件」とその後の「情夫側の親族が次々と18人も怪死した謎」をベースに、当時世間で話題になっていた様々な猟奇事件をないまぜにしてつくられたとされている(東雅夫・著『なぜ怪談は百年ごとに流行るのか』より)。
こうした浄瑠璃・歌舞伎作品は、現代のようにネットニュースやワイドショー、週刊誌のなかった当時、民衆の「ゴシップ」として楽しまれたものだそうだ。見に行った民衆同士が「あんな事件があったんだってね」「この話はあの事件がもとらしいよ」と噂することで日々の憂さを晴らす、そんな現代に通ずる楽しみ方をしていたという。
文芸評論家の東雅夫は著書の中で、「虚実皮膜」がエンターテインメントにもたらす効用について、
「小説や演劇といった虚構(フィクション)と、随筆などに記された実録とがあたかも相互に影響しあうかのようにして、ひとつの系(サイクル)が形成されてゆく」(『なぜ怪談は百年ごとに流行るのか』(東雅夫・著/学研新書)
と述べている。