「ナンバーワンよりオンリーワン」。こんな風に個性が重んじられる時代。
安全面から組体操や棒倒しが運動会からなくなって、成績は順位が発表されなくなった時代。
IT企業の社長もバイトに明け暮れる大学生も、ユニクロの服を着てコンビニで昼食をとる時代。
直木賞作家、朝井リョウは平成を「個人間の対立をなくそうとしていった時代」と表現する。
最新作『死にがいを求めて生きているの』には、平和が成立した時代に育った20代を中心に、学生団体に没頭する大学生、着飾ってしまうSNSのプロフィール、イライラしつつも見てしまうTweet……よくある風景の裏から人が狂っていく様が描かれる。

争いはなくなればいい。きっと、どの時代の人も願ってきた。明日の食事に困るわけでもなく、キリキリとした競争もない。幸せじゃないか。
でも、そこには新しい地獄がある。
対立は本当に失われるべきなのか、それとも――
「あらゆることがただ繰り返されている日々の中で、何が生きがいになり得るのか」
就職活動には内定という終わりがあるが、人生にはゴールがない。平和で争いのない時代、自動的に運ばれた毎日の先に何があるのだろう? 将来に対するぼんやりとした不安が人を駆り立てる――。
受賞作『何者』で、SNS時代における就職活動に奔走する大学生を描いた朝井。新作『死にがいを求めて生きているの』でどんな物語を紡ぐのか。
もともとこの企画は、小説家の伊坂幸太郎さんが「対立」をテーマに複数の小説家と原始から未来までの歴史物語をバトンリレーのように書こうとお声がけくださったものでした。
私は、平成しか書けないな……という気持ちもあり、この時代を担当させてもらいました。大先輩を目の前に偉そうですよね。

例えば、中世・近世を担当された天野純希さんは源氏と平氏、信長と光秀などの対立関係を書く、昭和・近未来を担当された伊坂さんは昭和で嫁姑の対立関係を書く。
そんな話を聞いていたのですが、「平成」で、となると、国をあげての対立も、時代を象徴するような個人間の対立も、なかなか思い浮かばなかったんです。自分でこの時代がいいと言ったけれど、悩んでしまいました。
逆に、平成は対立が奪われていった時代だったのではないか?
私は平成元年生まれ。対立について書くことが思い浮かばないと悩んだとき、初めてこう考え始めるようになりました。対立によって人が磨き上げられていくのではなく、自分の内なる個性が重要視されてきた世代なのかな、と。
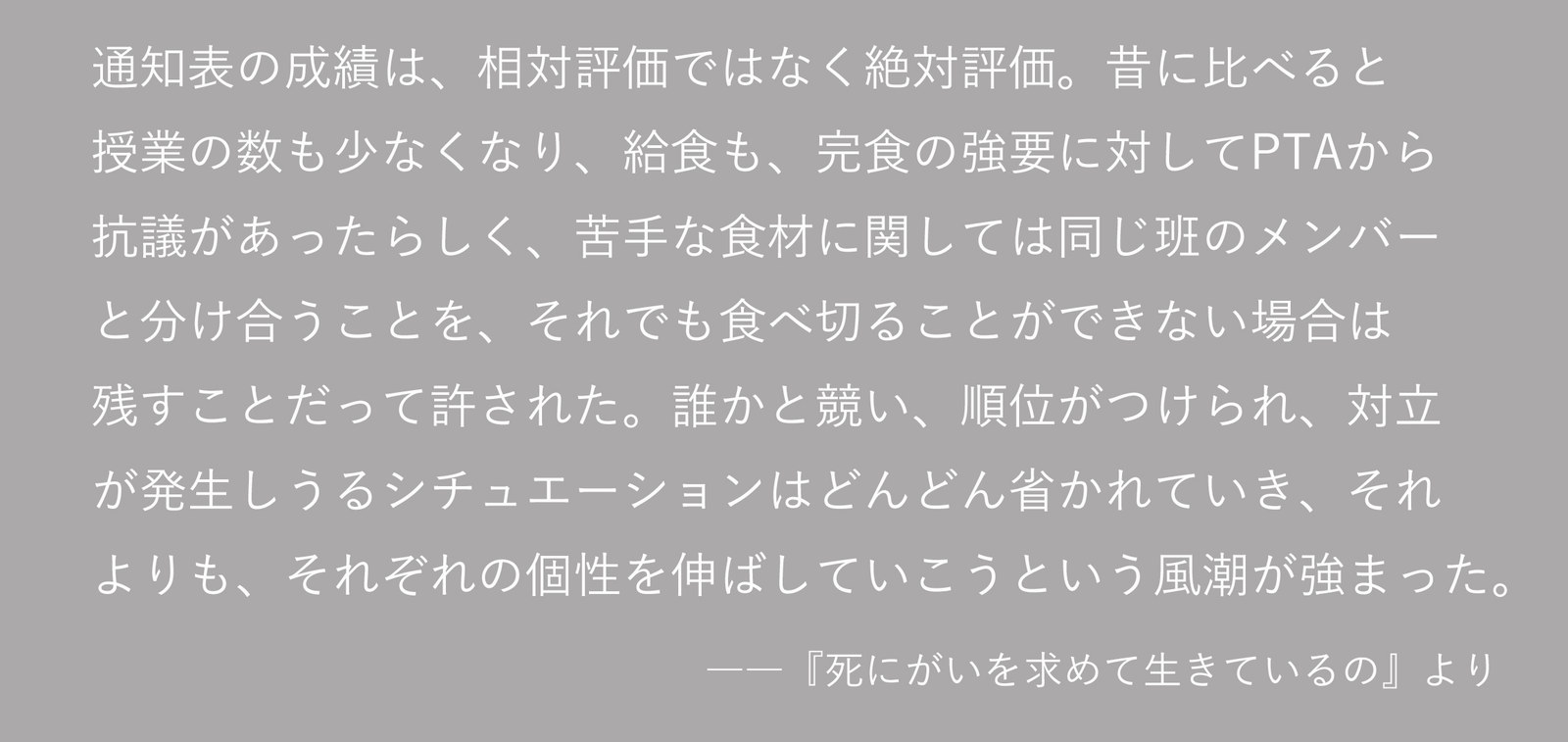
この作品を書いているとき、ある目上の方が「昭和は『男はこう、女はこう』というような、外部からの決めつけがたくさんあった。苦労や抑圧はあったけれど、問題意識を見つけやすいという意味では楽な部分もあった。
逆に平成は決められたレールがないから、自分で自分のことを見つけないといけない。また別の苦しみがあるんだろうね」とお話をしてくださったんですけれど、本当にそう思います。
「対立をなくそう」も「自分らしく」も、考え方はもちろん素晴らしいけれど、同時に、対立がなければ自分の存在を感じられない人の存在が炙り出される。自分らしさとは何か、自分とは何かということを自ら考え続けなければならないことによって、新しい地獄みたいなものも生まれる。
それは、外部から決めつけられる痛みとは全く別の、勝手に自分を毒していく痛みというか、自分を内側から腐らせていくような感覚だと思うんです。
自分が持っているモノの幻感
「特別な誰か」になりたくて、ボランティア活動に勤しんだり、無人島に行く様をSNSで投稿したり。そんな風に焦燥し、奔走する『死にがいを求めて生きているの』の各登場人物は、朝井自身を投影させたという。大学在学中に小説家としてデビューした彼は、会社員として働きながら男性としては最年少で直木賞を受賞した。「特別な誰か」に違いない。それでも平成に地獄を感じたのは、何故か?

『黒子のバスケ』脅迫事件の犯人の渡邊博史受刑者の吐露に、秋葉原通り魔事件の加藤智大受刑者が回答した手記がとても印象的だったんです。あまりに理路整然としていて絶句しつつ、自分が普段考えていたことがそのまま言葉にされている、と感じました。
渡邊受刑者は、夢破れたワーキングプアとして「極端な行動」や「対抗する存在」を作らないと社会との『つながりの糸』が持てない切迫感があった、と話していました。
つまり、『黒子のバスケ』の原作者を脅迫していたのは、原作者を傷つけるためではなく、自分が生きていくためだった、と。でも、逮捕されたことでそれすら失われてしまい「出所後、どう生きていけばいいのかわからない。多分自殺すると思う」というようなことを述べていたんです。
これに加藤受刑者は「あなたは人を殺さずして有名な犯罪者になれたのだから、その肩書きを活かして犯罪者心理の真実を世の中に伝えていく、というようなことをすればいいのではないか。犯人という肩書きは、一生消えることのない『つながりの糸』なのだから」というようなアンサーを返していました。
読みながら、返す言葉がないというか、自分の中にある“あえて言葉にしないようにしていた考え”みたいなものをそのまま言葉にされたような感覚がありました。同時に、私にとっての『つながりの糸』はきっと小説で、それがなかったら何に『つながりの糸』を託していたのだろう、と考えました。他者を傷つける行為に走らなかった、とは全く言えないなと。
そして、こういった自分と社会との繋がりについて考え続けた結果他者を傷つける行為に走る人って、男性が多いんですよね。そのことも、自分と彼らは何も違わないという気持ちをより強くしています。このあたりの考えは今回の小説にかなり反映されています。

『つながりの糸』を求める気持ち自体はおかしなことではないのに、どこかでズレていってしまうのはなぜなのか。小説の中では、どちらに振り分けるでもなく、いろいろな例を書いたつもりです。
現実でも、例えば、大学のレポートを求められてもいないのに英語で提出するとか、社会に対して熱く語り合う仲間を求めてシェアハウスに入り浸るとか、無人島で過ごした経験を高々と掲げるとか、大小さまざまなことに対して『つながりの糸』を求める気持ちを敏感に読み取ってしまう癖があります。
何かしていないと不安になる。何もない人生への焦燥……。
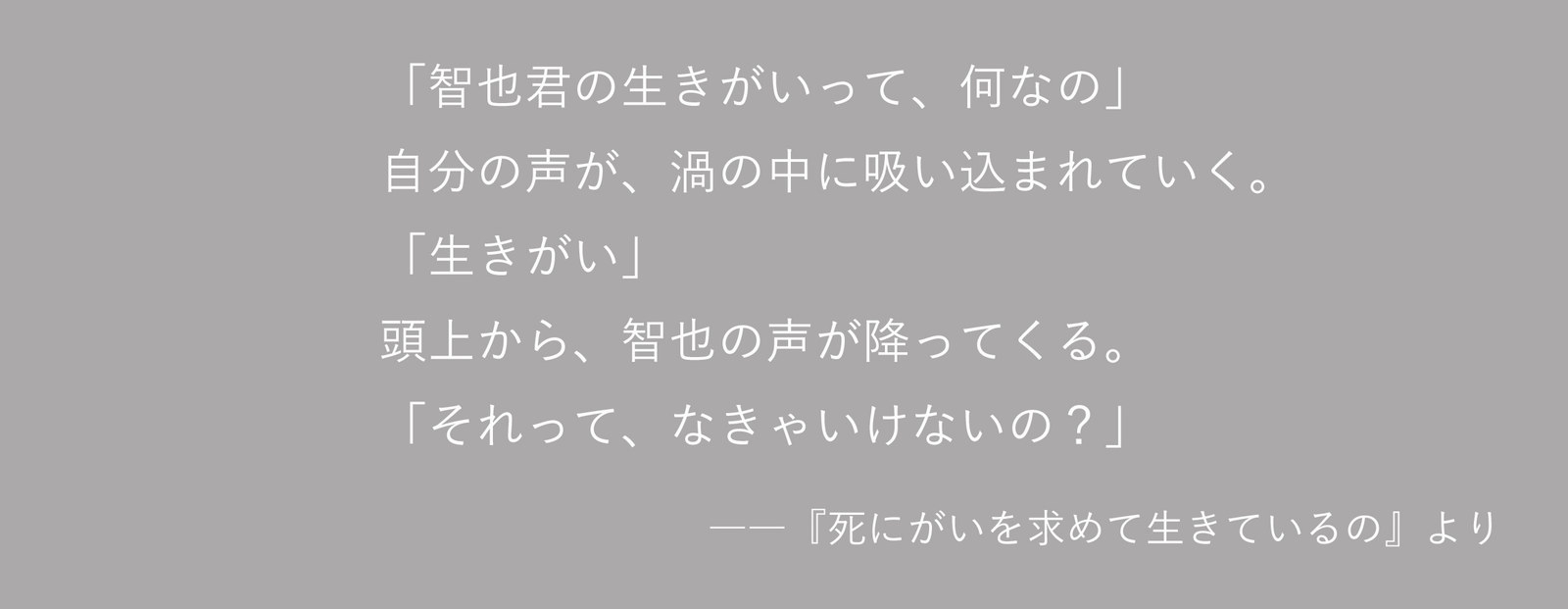
私にとっての『つながりの糸』への執着は小説を書いていることなんですよね。それは子どものころからずっとそう。小説を書くことが好きな気持ちと同様に、「小説書いている子どもってすごくない?」みたいな気持ちも絶対にあった。虚栄心がすごく強いんですよ。
投稿する賞、選考委員の面々、タイミング。何か一つでも違っていたら、今の状態はない。ものすごく幸運が重なって小説家としてデビューできただけで、表現欲と莫大な虚栄心だけ抱き続けていたらどうなっていたのか想像するのも怖いです。
ただ、私が私でなかったら、今の私の発言を読んで「そんなこと言ったって直木賞とかとってるじゃないか」みたいに思うんですよね。
でも、小説は人によって評価が揺らぐものであり、絶対的な物差しがない。どんな賞だって、一時的で個人的な評価をいただいただけ。『何者』を書いたのが40歳の作者だったとしたら、どんな選考になっていたんだろう、とか考えると止まらなくなります。
常に自分に疑いがあるんです。
世界共通の物差しがあって、実力が明確にわかる分野の住人だったら、もっと自分のことを信じられるのかな、と思います。医者として〇人の命を救ったとか、アスリートとして世界〇位の記録保持者だ、とか。

小説を書きながら無能感を抱くことがすごく多い。だって、道で倒れている人に小説は差し出さないから。
私は当初、会社員をやりながら小説を書いていたのですが、とにかく時間のない生活の中で最初に削ったのが読書の時間でした。
なので最近は、「誰かのため」という気持ちを起点にしないようにしています。誰かのために役に立ちたいなら、それこそ医者か、衣食住を直接支えられる農家などを目指した方がいい。
じゃあ、なぜ小説を書いているのか、というと……。
もちろん純粋に書くのが好きだからという気持ちが土台にありますが、言葉の選択肢を得たいから、だと思います。
いま、人は言葉でしか他人とコミュニケーションが取れないですよね。今後画像や音をそのまま共有できるようになるかもしれないけれど、今は言葉でしかやりとりができない。
それってつまり、本当は言葉で表現することができないものも、無理やり言葉というものに当てはめているってことだと思うんです。
例えば、アルコールを摂取していい状態であることを表す言葉が「二十歳」って、おかしくないですか。少年法でいう責任能力だって、「十八歳」という言葉で無理やり線引きしてますけど、本来そこで線引きできないはずです。95歳の親を看ていた75歳が老々介護の果てにその親を殺したとして、当てはまる言葉は「殺人」なのかな、とか。
とにかく、世の中にあふれる感情や現象に対して、言葉が足りてないな、と感じます。
だから、言葉でしかコミュニケーションを取れない以上は、言葉の選択肢はできるだけ多く持っていた方がいいと思うんです。自分はそれを小説から受け取っている感覚があるから、物語を書いて生きている自分をかろうじて許せているのかもしれません。
「黒と白の間を何通りの言葉で表現できるか?」みたいなことが大切だと思うんです。その中で新たな言葉の選択肢を見つけた時は、非常に嬉しい。
でも、それを映画や漫画やゲームや、本以外のいろんなものから受け取る人もたくさんいますよね。だから、小説が一番、とかも思えないんです。自分の存在は常に怪しい。疑いの目が常にある。
スペシャルな経験がないのに「自分らしさ」なんて見つけられるのか

平成は絶対的な物差しがなく、誰にでもチャンスがある時代。それは「持っているモノ」ですら不安定な時代とも言える。物語と自身が交錯するように、朝井も「自分らしさ」の地獄にいた。作家として「スペシャルな経験がないことがコンプレックスだった」と話す彼だが、最近ある言葉に出会った。
私は「リア充爆発しろ」みたいな感覚がないんです。そもそも「不幸な経験がある人こそ創作者に向いている」ということも信じていないし、その創作者の不幸合戦って不毛だと思っています。不幸ゆえの反逆心は、創作の上で一瞬は光ると思うんですけど、不幸合戦の先って究極「死」なんですよね。「いい作品を書くためには死んだ方がいい」って、おかしいじゃないですか。
自分には最大公約数だという自覚が強くあります。浜崎あゆみを聴いてしっかり感動し、地方の公立でそれなりに楽しく過ごし、特殊な趣味などもありません。だから「大発見」のある物語を書くことは目指さないようにしています。
『死にがいを求めて生きているの』も、平成のアイテムや言葉を使って、これまで散々書かれてきたようなことを書き直しているんだと思います。例えば80年前に書かれた『山月記』は、勝手に、とても似たものを感じていたりします。
大発見のある物語を書くことのできる小説家の存在が、ずっとコンプレックスでした。
でも、それをある先輩作家に相談したら「大発見もなしに、細々としたズレみたいなもので1冊の物語を書けるのは長所なんじゃないの。そこを伸ばせばいいんじゃないの」とアドバイスをいただいて、開き直った部分はあります。
「物語で大事なのは、物じゃなくて語りの方だ」
最近読んだ藤田祥平さんの小説にこんな言葉が出てきて、すごく印象的でした。自分はスペシャルな経験を持っていないのだから、なんてことない「物」を「語り」で成立させていこう、そういう気持ちになりました。
総理大臣になったから、死の淵を見たから、いい物語が書けるわけではない。どんなモノも語りによって物語になる。

物差しがない時代、対立のない毎日。自分が誰なのかわからなくなるのは当然なのかもしれない。しかし、平成元年生まれの小説家は、先輩に相談したり、誰かの小説で言葉を見つけたり「特別ではない方法」で少しずつ前に進んでいる。
「それしか考えなくていい状態」ってすごくデトックスになると思うんです。
小説の中ではカルト的なもの、学生運動的なものを、「それしか考えなくていい状態」の例として書いたのですが、私自身、会社員時代がそうだったと思います。降ってくる仕事に応えることに精いっぱいで、毎日とにかく必死で、「この仕事は社会にとって何のためになるの?」なんて一切考えなくてよかったんです。
でも、いざ専業作家になると「なぜ今この物語を書くのか」とか「小説を書いても人は救えないな」とか、考える時間がいっぱいある。作家の自殺が多い理由って納得できてしまう。
平井堅さんの『ノンフィクション』に出てくる「惰性で見てたテレビ消すみたいに生きることを時々やめたくなる」という歌詞に共感するぐらいに。
多分、自分の意味とか仕事の価値とかって、根詰めて考えちゃいけないんですよね。
私は、バレーボールが好きなので、都内の体育館によく行くのですが、その時は「ボールを落とさない」ということだけを考えるので、精神的にとても健康だなと感じます。
子どもを産んだ友人は、何よりも自分について考える時間が減ったと話していて、それによって助けられている部分も確かにあると言っていました。自分が面倒を見ないと死んでしまう生き物がいるという環境は、自分についての考え事を否応なく減らしてくれるんですよね。
どこにも物差しがなくて自分で自分を見つけなければならないからこそ、何も考えなくてもいい時間……がありがたいんだと思います。
小説の最後のほうは、そういうものを一切見つけられない、自分のことを考え続けることをどうしたってやめられない気持ちをどうすれば自分や他者への攻撃へすり替えずに済むのか、とても考えながら書きました。書きながら、今の自分の最上級を尽くしたつもりでも、やっぱり言葉の選択肢がまだまだ足りてないな、と、実感しました。
